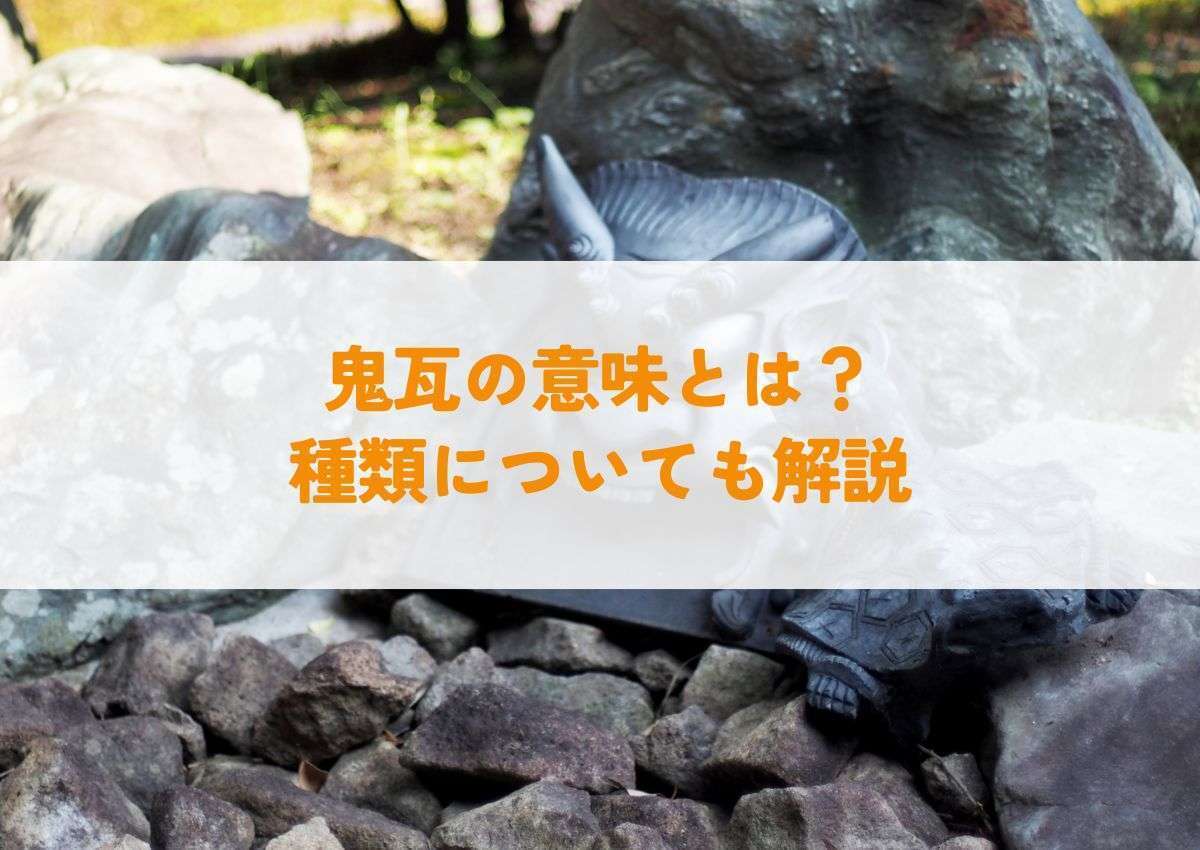鬼瓦は、日本の伝統的な建築物に見られる、独特な装飾要素の一つです。
しかし、鬼瓦は単なる装飾品ではありません。
その起源や役割、そして種類には、深い意味と歴史が隠されています。
この記事では、鬼瓦の意味と種類、鬼瓦の由来や役割、鬼師について解説します。
□鬼瓦の意味とは?
鬼瓦にはどのような意味があるのでしょうか。
鬼瓦は、日本式建築物の棟の端などに設置されている板状の瓦です。
主に厄除けや飾りとして用いられますが、雨水が屋根に浸入するのを防ぐ役割も担っています。
その歴史は古く、約1400年前の飛鳥時代まで遡り、様々なデザインが存在します。
1: 鬼瓦の起源と歴史
鬼瓦の起源は、諸説ありますが、最も有力な説の一つに、古代ギリシャ神話に登場する蛇髪の怪物メドゥーサが挙げられます。
メドゥーサは、その恐ろしい姿で人々を石に変える力を持つとされ、古代ギリシャでは魔除けとして寺院や宮殿の入り口にその像が飾られました。
このメドゥーサの像が、シリアのパルミラ遺跡にある入り口の上に設置されていたことから、それが鬼とかわり鬼瓦になったと言われています。
2: 鬼瓦の役割
鬼瓦は、厄除けや魔除けの役割を持つとされています。
鬼瓦に鬼のデザインが施されているのは、鬼を味方につける、鬼が厄を払ってくれるといった意味が込められています。
また、雨仕舞の役割も担っており、雨水が屋根の中に浸入するのを防いでいます。
3: 鬼瓦のデザイン
鬼瓦のデザインは、時代や地域によって大きく異なります。
代表的なデザインには、以下のものがあります。
・鬼瓦:鬼の顔や角、牙などをモチーフにした、最も一般的な鬼瓦。
・獅子瓦:獅子の顔や体をモチーフにした鬼瓦。
・龍瓦:龍の顔や体をモチーフにした鬼瓦。
・唐草瓦:唐草模様をモチーフにした鬼瓦。
・花瓦:花や植物をモチーフにした鬼瓦。
鬼瓦のデザインは、その時代や地域の歴史、文化、信仰などを反映していると言われています。
□鬼瓦の種類と役割
鬼瓦は、屋根の上の位置によって、名称が異なります。
棟瓦の端に乗せられているものが鬼瓦、軒先へ下っているものが下り鬼、軒先の一番端に乗せられているものが隅鬼と呼ばれています。
また、鬼瓦は、雄と雌があります。
雄は口が開いていて角が大きく、面相が厳しい一方、雌は口を閉じていて角が小さく、面相が優しいのが特徴です。
*鬼瓦を制作する鬼師
鬼瓦は、鬼師と呼ばれる専門の職人が一つ一つ手作りで制作しています。
鬼師は、瓦を成形し、彫刻を施し、焼き上げるまで、すべての工程を熟練の技術でこなします。
鬼師の技術は、代々受け継がれてきた伝統的な技法であり、鬼瓦を通して、日本の伝統文化を現代に伝えています。
□まとめ
鬼瓦は、単なる装飾品ではなく、古来より人々の暮らしを守ってきた重要な存在です。
厄除けや魔除け、雨仕舞など、様々な役割を担い、その歴史や文化は、日本の伝統建築の奥深さを物語っています。
鬼瓦のデザインや種類、そして鬼師の技術を通して、日本建築の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。